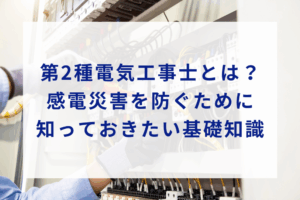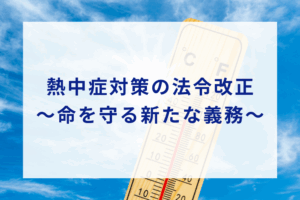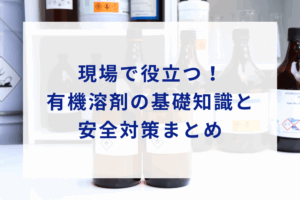1. はじめに
石綿(アスベスト)は、かつて建築材料として広く使用されていました。耐火性・断熱性に優れた特性を持つため、さまざまな建材に含まれていましたが、健康被害のリスクが判明し、現在では全面的に使用が禁止されています。しかし、過去に建築された建物には依然として石綿含有建材が残っており、解体・改修工事の際に適切な処理が求められています。
本記事では、一般建築物における石綿含有建材の種類や年代ごとの使用状況、調査の必要性や方法、適正な処理方法について詳しく解説します。
2. 一般建築物における石綿含有建材とは?
2-1. 石綿が使用されていた建材の種類
石綿は、以下のような建材に含まれていました。
- 壁材:スレート、石綿セメント板、吹き付け材など
- 天井材:ロックウール吸音板、化粧石綿板
- 床材:塩ビタイル、クッションフロア
- パイプやボイラーの断熱材
- ガスケットやパッキン
これらの建材は、主に耐火性や断熱性を高めるために使用されており、特に工場や公共施設、マンションの共用部分などで多く見られます。
2-2. どの年代の建物に多く使用されていたか
日本では、1960年代から1980年代にかけて石綿が多く使用されていました。具体的には以下のような流れで規制が進んでいます。
- 1960年代~1980年代:広範囲で使用される
- 1990年代:徐々に規制が強化される
- 2006年:石綿の使用が全面禁止となる
そのため、2006年以前に建てられた建築物には、石綿含有建材が使用されている可能性があることを念頭に置く必要があります。
3. 一般建築物での石綿調査の必要性と方法
3-1. なぜ調査が義務となったのか?
石綿は、長期間吸い込むことで中皮腫や肺がんなどの健康被害を引き起こす可能性があります。そのため、建築物の解体・改修時に石綿が飛散しないよう、事前調査が義務化されました。
2023年の法改正により、一定規模以上の解体・改修工事では、専門業者による石綿調査が必須となりました。
3-2. 石綿含有の可能性がある建材の見分け方
石綿含有建材は、見た目だけでは判断が難しいため、専門的な調査が必要です。調査方法としては以下の3つがあります。
- 目視調査:建材の種類や製造年をもとに判断
- 試料採取・分析:一部を採取し、顕微鏡分析などで含有の有無を確認
- 書類調査:建築時の設計図や施工記録を確認
3-3. 専門業者に依頼する際のポイント
石綿調査を依頼する際は、以下の点に注意しましょう。
- 国が認定した専門業者に依頼する
- 見積もりや調査方法を事前に確認する
- 安価すぎる業者は注意(違法な処理のリスクがある)
4. 石綿含有建材の処理方法と法規制
4-1. 石綿廃棄物の処理方法と費用
石綿含有建材の処理には、以下の方法があります。
- 封じ込め:既存の建材をそのまま残し、飛散防止措置を施す
- 除去:石綿含有建材を撤去する(飛散対策が必要)
- 囲い込み:建材を密閉して飛散を防ぐ
処理費用は建材の種類や建物の構造によって異なりますが、数十万円~数百万円規模になることが多いため、計画的な予算立てが必要です。
4-2. 違法な処理を避けるためのポイント
違法な処理を行うと、罰則や健康被害のリスクが高まるため、以下の点に注意しましょう。
- 無許可業者による撤去はNG
- 適切な防護措置を行う
- 自治体の指導に従う
違法処理が発覚すると、企業や個人に罰則が科される可能性があるため、適正な処理を徹底しましょう。
5. まとめ
一般建築物における石綿含有建材は、現在も多くの建物に残っています。そのため、建物の解体・改修時には、適切な調査と処理を行うことが不可欠です。
- 石綿は2006年まで使用されていた
- 調査は専門業者に依頼する
- 処理は適正な方法で行う
今後も、法規制の強化や新たな基準の設定が行われる可能性があります。石綿のリスクを正しく理解し、適切な対応を心がけましょう。