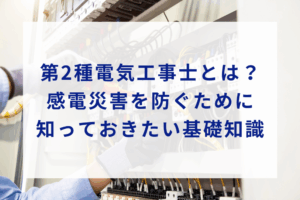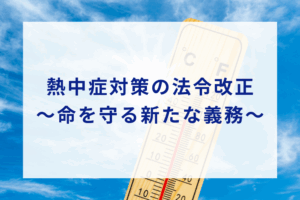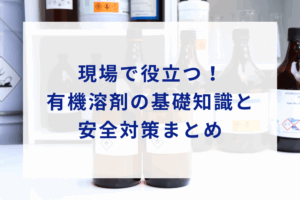私たちの生活や産業の中で広く使われている有機溶剤。しかしその便利さの裏には、人体への深刻なリスクが潜んでいます。有機溶剤中毒は、見落とされがちな職場のリスクでありながら、正しい知識と対策で防ぐことができます。本記事では、有機溶剤中毒の症状や実際の事例、そして予防のために不可欠な換気・保護具・作業方法などをわかりやすく解説します。
有機溶剤中毒とは?
有機溶剤中毒とは、有機溶剤を吸引または皮膚から吸収することにより、人体に有害な影響を及ぼす症状のことです。有機溶剤は、塗料や接着剤、洗浄剤、インクなど多くの製品に含まれ、工場や建築現場、ネイルサロンなどさまざまな場所で使用されています。
吸引や皮膚吸収による中毒の症状
有機溶剤中毒の主な原因は、吸入または皮膚からの吸収です。代表的な症状には以下のようなものがあります:
- 初期症状:目や鼻の刺激、喉の痛み、軽いめまい、倦怠感
- 中等度の中毒:頭痛、吐き気、集中力低下、運動失調
- 重度の中毒:意識障害、けいれん、呼吸抑制、最悪の場合は死亡に至るケースも
皮膚からの吸収でも、炎症や発疹、かぶれを起こすだけでなく、全身症状につながることがあります。
特に、密閉空間での作業や、換気が不十分な環境下では、有機溶剤の蒸気が室内に充満し、中毒リスクが非常に高くなります。
実際の労災事例とその原因
事例1:密閉空間での塗装作業中に意識不明
建築現場の狭い室内で塗装作業をしていた作業者が、適切な換気設備がないまま作業を続け、1時間後に意識を失い搬送されました。原因はトルエンなどの有機溶剤の蒸気を大量に吸い込んだことでした。
事例2:ネイルサロンでの慢性中毒
ネイリストとして10年以上働いていた女性が、日常的にアセトンや酢酸エチルなどの揮発性溶剤を使用していたことで、慢性的な頭痛や吐き気を訴えるようになりました。換気が不十分で、保護具の使用もされていなかったことが原因とされました。
事例3:清掃業者の洗剤使用による皮膚障害
ビル清掃を行う作業員が、床用洗剤に含まれる溶剤を素手で使用し続けた結果、皮膚炎を発症。MSDSを確認していなかったことが背景にありました。
これらの事例からもわかるように、「身近な作業」にこそ、見落とされたリスクが潜んでいます。
有機溶剤中毒を防ぐための対策
中毒を防ぐには、「環境整備」「保護具の使用」「教育・講習」が不可欠です。
適切な換気
作業場の換気を十分に行うことが、有機溶剤中毒を防ぐ第一歩です。具体的には:
- 局所排気装置(フードやダクト)の設置
- 定期的な換気(窓の開放、換気扇の使用)
- 換気装置の点検・メンテナンス
換気が不十分だと、有機溶剤の濃度が急激に上昇し、短時間でも中毒を引き起こす可能性があります。
保護具の使用
作業内容に応じた保護具を正しく使用することも重要です。
- 防毒マスク:蒸気やガスの吸入を防止
- 保護手袋:皮膚からの吸収を防ぐ
- ゴーグル:目への刺激を防止
- 作業着や前掛け:皮膚への付着防止
MSDS(安全データシート)を確認し、取り扱う有機溶剤に応じた保護具を選定しましょう。
正しい作業方法と教育
作業者が有機溶剤の危険性を理解し、安全に作業を行えるよう、定期的な教育や講習が必要です。
- 有機溶剤の性質・リスクの周知
- 正しい作業手順の徹底
- 緊急時の対応方法(中毒時の処置、通報先)
法令により、一定の条件下では「有機溶剤作業主任者」の選任が義務づけられています。この主任者は、作業環境の点検や作業者の指導を行う責任があります。
身近にある有機溶剤の例
「自分の職場には関係ない」と思っていても、有機溶剤は意外なところに潜んでいます。たとえば:
- ネイルサロン:除光液やジェルリムーバー(アセトン)
- 清掃業:床用剥離剤、洗浄剤(イソプロパノール)
- 建築業:塗料、接着剤(トルエン、キシレン)
- 印刷業:インク溶剤、洗浄液(MEK)
これらの業務に従事する方は、定期的に自分の作業環境や使用している薬剤を見直し、安全対策が講じられているか確認することが大切です。
まとめ
有機溶剤中毒は、身近な作業の中で誰もが被害者になりうるリスクです。しかし、正しい知識を持ち、適切な換気や保護具を使用し、安全な作業方法を徹底することで、未然に防ぐことが可能です。
特に事業者は、作業者の健康と安全を守る責任があり、法令に基づく教育や設備の整備が求められています。これを機に、自分自身や職場の環境を見直し、必要な対策が取られているか確認してみましょう。